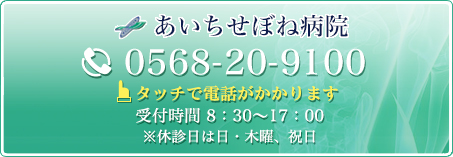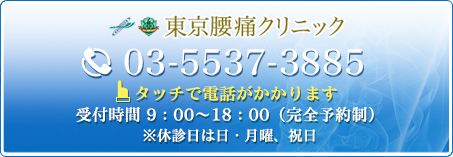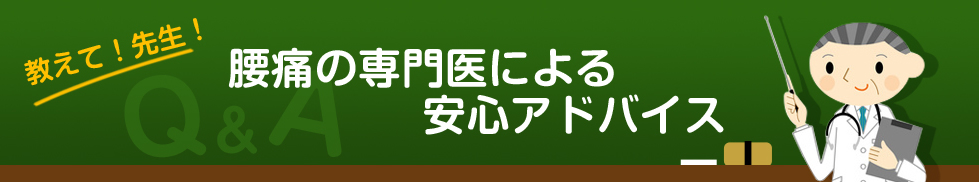トップページ > リハビリについて
リハビリについて
質問と回答
リハビリって何?

リハビリとは「リハビリテーション=Rehabilitation」の略で、ラテン語のre(再び) – habilis(適した)という言葉に由来します。
病気や怪我をはじめ、あらゆる原因によって低下した心身の機能を向上・適応させ、語源の通り再び社会生活に適応した状態になるために行うすべての行為を指します。
通常、医療行為は、診察・治療・各種検査など、受身的に行われるのが一般的です。一方リハビリテーションは、 患者様が主体となって取り組んでいただくものです。
病院、特に整形外科でのリハビリというとストレッチやマッサージなどがイメージされますが、それらはごく一部であり、最大最良の効果を得るためにはリハビリ室で行われる行為のみならず、ご自身で行うケアや運動、日常生活での意識などが非常に重要です。
リハビリはどこでうけられるの?
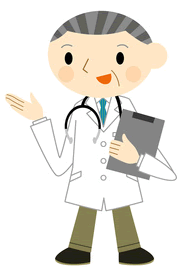
保険の種類や病気など、状況によって異なりますが、主に病院やクリニックといった医療機関で受けることができます。また、介護保険下であればデイケアと呼ばれる通所リハビリテーション施設に加え、セラピストが自宅まで来てくれる訪問リハビリもあります。
制度や対象となる疾患によって適切なリハビリが受けられる施設は異なりますので、かかりつけ医や担当ケアマネージャなどに相談してみるといいでしょう。
リハビリの先生にはどんな資格があるの?

代表的なものとして理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)が挙げられます。これらはいずれも国家資格で、3年~4年の専門学校・大学を卒業し、国家試験に合格する必要があります。
理学療法士はPT(Physical Therapist)と呼ばれ、ケガや病気でうまく体を動かせなくなった方に対して、主に立つ、座る、歩く、寝返りをするなどの基本的な動作の獲得を目指して様々な介入を行う職種です。整形外科(ヘルニアや骨折など)、脳神経系(脳梗塞など)、循環器系(心臓や肺)、小児領域など、幅広い領域が対象となります。病院以外では、高齢者施設などで「健康を維持する」「身体機能低下を予防する」ことを目的とした活動を行ったり、スポーツトレーナーとして活動したり、活躍の場は多岐にわたっています。
作業療法士はOT(Occupational Therapist)と呼ばれ、食事や入浴、家事など応用的な動作の獲得を目指して介入を行う職種です。また、作業療法士は身体的な障がいだけでなく、精神に障がいがある方も対象として活躍していることが特徴です。
PTとOTは似たような介入を行うことも多いですが、細かいところでは介入対象や得手不得手が分かれています。
言語聴覚士はST(Speech Language Hearing Therapist)と呼ばれ、病気や加齢などによって低下した「話す」「聞く」「食べる」といった機能の獲得・向上を目指して介入を行う職種です。子どもから高齢者の方まで幅広い年代の発声や発音、言葉の発達、吃音、難聴、嚥下(飲み込み)などを対象としています。
これらリハビリテーション専門職は必要に応じてそれぞれが協力して患者さんのリハビリテーション達成に向けて取り組みますます。
病院のリハビリと接骨院とは違うの?
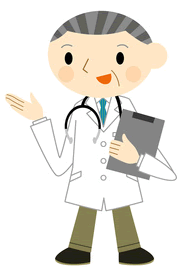
接骨院を開業されているのは「柔道整復師」という資格を持つ人になります。マッサージや運動などを行うことから前述の理学療法士と混同されることが多い資格ですが、その本質は大きく異なります。
柔道整復師は開業権が認められており、接骨院やほねつぎといった名称を用いて開業することが可能です。
ただ、柔道整復師の行う業務は医業類似行為と呼ばれ、急性の打撲や捻挫、脱臼、骨折等を対象とした資格であり、それ以外の慢性的な病気等への処置は健康保険の適応範囲外となっています。そのような適応範囲外の疾患に対して医療保険を用いてマッサージ等を行うことが、時に療養費の不正請求として問題になることがあります。
一方、理学療法士は「医師の指示のもと」理学療法を行う資格であるため、主に医療機関や高齢福祉施設に勤務しています。柔道整復師とは異なり開業権は認められておらず、自分で○○院といった店舗を出店しても医療保険を使用することはできません。あくまで「医師の指示のもと」健康保険が適応となり、窓口支払いの自己負担は0~3割となります。また、前述の通り対象とする病気や障害も大きく異なります。
ヘルニアなど腰痛・しびれについてのお問い合わせ・診療予約