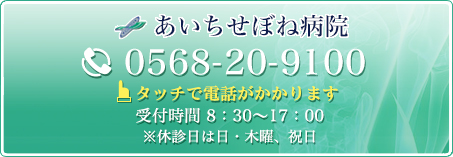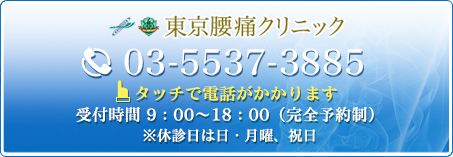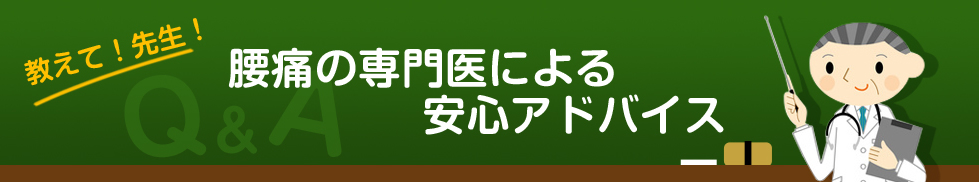トップページ > 麻酔、病院での検査について
麻酔、病院での検査について
質問と回答
麻酔について教えて

まず麻酔という言葉ですが、手術による苦痛を取り除くため、薬を使って痛みをはじめとした感覚をなくすことを指します。
脳や脊髄神経、手や足先の末梢神経まで、一時的でしかも後遺症を残すことなく神経の働きを抑えます。麻酔法は、意識がなくなる全身麻酔と、意識はあっても痛みを感じなくなる局所麻酔法の2つに大別されます。
全身麻酔について教えて
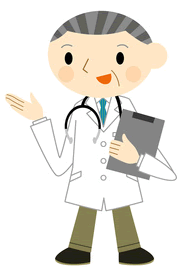
手術の際に苦痛を伴わないように、また患者さんが動いてしまわないように全身に麻酔をかけることを全身麻酔と言います。全身麻酔では意識が消失するため、記憶にも残りません。
全身麻酔では患者さんは苦痛を訴えることができないので、麻酔科医が患者さんの状態を常に注意深く観察しています。
全身麻酔には、ガスを吸うことで麻酔をかける「吸入麻酔法」と、点滴から薬を注射して麻酔する「静脈麻酔法」があります。患者さまの健康状態や年齢、持病などを考慮し、もっとも安全で適切な麻酔方法を選択します。
全身麻酔は危険じゃないの?

日本麻酔科学界が行った調査では、麻酔が原因で死亡する割合は22万症例に1例と報告されています。麻酔専門医が適切な管理下に全身麻酔を行なえば、麻酔は極めて安全と言えると思います。
「麻酔は怖い」「麻酔から目が覚めなかったらどうしよう」と心配される患者様が多くいらっしゃいますが、たとえ副作用が出たとしてもそのほとんどは軽微で一過性のものであり、手術後48時間以内にほぼ解決します。もっとも発生頻度が高い合併症は、のどの痛み、声のかすれ、頭痛、吐き気、めまい、腰痛、目の違和感、手術後の震えなどです。
局所麻酔について教えて
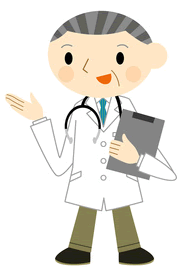
局所麻酔とは、末梢神経に麻酔薬を注入して、意識を保ったまま痛みの感覚を麻痺させる麻酔法です。局所麻酔薬を噴霧したり塗布する表面麻酔や、皮下への注射による浸潤麻酔、脊髄神経や太い神経の近くまで針をすすめ、局所麻酔薬を注入する伝達麻酔などがあります。
例えば胃カメラなどでは、のどに表面麻酔を行うことで安楽に検査が受けられますし、抜歯や小さな傷を縫う時には注射による浸潤麻酔が行われ、無痛で治療を行うことができます。腰痛に使われる仙骨硬膜外ブロックなどは伝達麻酔の一種です。
局所麻酔の危険性について教えて

局所麻酔は意識を保ったまま行う方法ですので基本的には安全と言えますが、鎮静剤を併用した局所麻酔では、呼吸不全から心臓停止にいたる重篤な合併症を引き起こすことがあります。鎮静剤を併用した局所麻酔は半分眠っているような状態になり、迷妄麻酔と呼ばれます。たとえ局所麻酔であっても、麻酔科医による十分な管理のもとで麻酔が行われる必要があります。
アメリカでは、手術室以外での麻酔科専門医以外の者による鎮静剤の使用で、6年間に89名が死亡したという報告があるほどです。
レントゲン検査では何がわかるの?
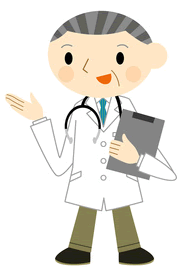
レントゲン検査は、放射線の一種であるX線を照射して写真をとる検査です。
人は、骨、筋肉、脂肪、血液などでできており、それぞれがX線を吸収する量が異なるため、その差を白黒の画像としてフィルムやモニターに表示することができます。たとえば背骨に関しては変形や骨折、ズレの有無、不安定性などを確認することができます。短時間で行え、苦痛もほとんどないため、まずはレントゲンを撮りましょうという病院も多いと思います。しかし、レントゲン写真では神経や椎間板などの組織が明確に写らないことから椎間板ヘルニアなどの診断には、他の検査を合わせて行う必要があります。
MRI検査では何がわかるの?

MRIとは、磁気と電波を利用して体の内部を画像化する検査で、放射線などは使用せず、人体に無害な検査と言えます。
検査時間が20分程度と長いことや機械の音が大きいなどの欠点はありますが、レントゲンではわからない神経や筋肉などの柔らかい組織を写し出すことができます。ただ、装置自体が非常に大きく高価なため、最新のMRI設備が整っている施設は多くありません。鮮明な画像検査を行えるのは大学病院をはじめとした一部の施設に限られます。
CT検査では何がわかるの?
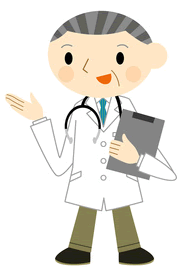
CT検査とは、レントゲンと同じX線をあらゆる方向から照射し、撮影することで身体の輪切り画像や、3Dの立体画像を写し出す検査です。
CT画像ではレントゲンよりもさらに詳しく骨の状態を評価することが可能です。レントゲン・CTによる骨を中心とした硬い組織の撮影と、MRIによる神経などの軟らかい組織の撮影を組み合わせることで背骨の状態をチェックすることが、治療方針を決定するうえで重要と言えます。
ヘルニアなど腰痛・しびれについてのお問い合わせ・診療予約