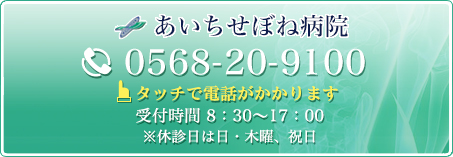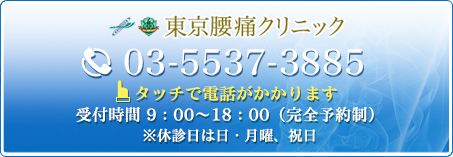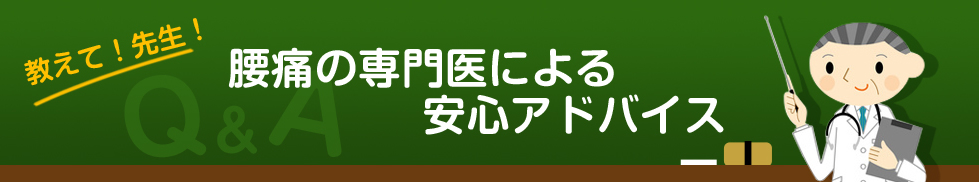トップページ > 頚椎症性脊髄症(頚髄症)・頚椎症性神経根症
頚椎症性脊髄症(頚髄症)・頚椎症性神経根症
質問と回答
頚椎症性脊髄症(頚髄症)、頚椎症性神経根症ってなに?

頚椎(首の骨)は、7個の骨が積み木のように連なった構造をしています。骨の内側には脊柱管という神経の通るトンネルがあり、そこを頚髄が通っています。そして、頚髄から分岐している神経根が、頚椎の骨と骨の間から腕や手に向かって伸びています。
この頚椎が加齢などにより変形する病気を頚椎症と呼び、この頚椎症によってトンネルの中を通る頚髄が圧迫される病気を「頚椎症性脊髄症(頚髄症)」、首から手先までつながる神経根が圧迫されて症状が出現する病気を「頚椎症性神経根症」と呼びます。聞きなれない難しい病名ですが、頚椎ヘルニアなどと併せて、首の病気を代表するものです。
頚椎症性脊髄症(頚髄症)と頚椎症性神経根症の症状は?
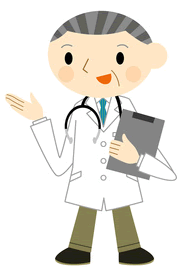
脊髄症(頚髄症)と神経根症は、どちらも首から手先にかけての痛みやしびれを引き起こします。筋力の低下や感覚の麻痺が起こることもあります。上に向くような動作で頚椎を後ろへ反らすと神経根が圧迫されるため、症状が強く出ます。
脊髄症(頚髄症)の場合は、左右両側に症状を引き起こすことが珍しくなく、重症化した場合は下半身にまで症状が及び、歩くことが困難になることもあります。
神経根症の場合は、通常、障害を受ける神経根は片側のため、左右どちらか一方の腕や手など限局した部分に症状が現れます。
頚椎症性脊髄症(頚髄症)、神経根症にはなんでなるの?

脊髄症(頚髄症)と神経根症、ともに前述の通り頚椎症による神経の圧迫が原因です。
頚椎症は、加齢や繰り返される負担によって引き起こされることがほとんどですが、加齢に伴う変性には個人差があり、どのような人に起こりやすいのか、また、何が原因で重症化しやすいのかなどについて、今のところ詳しいことは分っていません。下向きでの作業や、首を反らす姿勢の繰り返しなども原因の一つと言われています。
頚椎症性脊髄症(頚髄症)、神経根症の治療はどんなものがあるの?
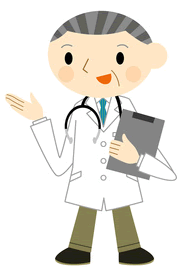
まずは適切な診断のためにレントゲンやMRI、CTといった検査で神経や骨の状態をチェックします。頚椎症性脊髄症(頚髄症)、神経根症の診断がついた場合、治療は多くの場合手術などを行わない保存療法が選択されます。
治療は、軽度の場合は頚椎に負担をかけないような姿勢や動き方の指導に始まり、症状の程度に応じて、消炎鎮痛剤の処方やブロック注射などを行います。また、リハビリでは頚椎牽引や温熱・電気治療などで症状の緩和を図ったり、首の筋肉のコンディションを整えたり、筋力を鍛えることで、頚椎に係る負担を減らします。他にも首の負担を減らすために、頚椎カラーと呼ばれる装具を首に装着することもあります。筋力低下や感覚麻痺などがある場合や、日常生活に支障があるくらい症状が強い場合などは手術が検討されます。
頚椎症性脊髄症(頚髄症)、神経根症の手術はどんなもの?

頚椎症性脊髄症(頚髄症)、神経根症の手術法としては、首の後ろ側から切開し神経の通り道を広げる「椎弓形成術」や、前方から切開して神経根の圧迫を取り除き、固定する「前方除圧固定術」などが多く行われています。
また、近年では、内視鏡を利用した非常に身体への負担が少ない手術も、限られた医療機関ではありますが行われています。内視鏡による手術は入院期間が短く、早期の社会復帰が見込めることが特徴で、高齢の方でも比較的安全に受けられることから注目を浴びています。手術に限らず、まずは整形外科、特に背骨(脊椎)専門の医師の診断を受け、適切な治療方針を相談することが大切です。
頚椎症性脊髄症(頚髄症)、神経根症を予防するにはどうしたらいいの?
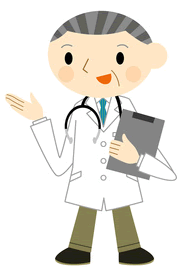
まずは頚椎に負担をかけないよう、正しい姿勢を心がけます。特に上を向くなどの首を大きく反らす動作は頚椎に負担をかけ、神経の圧迫を強める原因となりますので避けた方が良いでしょう。生活の中ではうがいや、洗濯物を干すときなどに注意が必要です。起床時に症状が強い場合などは、枕の高さなども関係があるかもしれません。
脊髄症(頚髄症)と神経根症は、ともに加齢に加えて、下向きの作業や、あごの上がった悪い姿勢でパソコンをする、仕事や家事などで首を反らすなど、日常生活の中で繰り返される負担や姿勢不良が原因となる場合が多いようです。日頃のちょっとした注意の積み重ねが予防に役立つでしょう。
ヘルニアなど腰痛・しびれについてのお問い合わせ・診療予約